(経理実務のポイント)固定資産の会計処理を全般的におさらいします!

こんにちは、ひめのです。
固定資産の会計処理については、ひとつだけでなく状況に応じてそれぞれ会計処理があります。
固定資産の取得→保有・評価→処分といった形で分類することができますが、それぞれの会計処理を全般的に知っておくことは実務上有用です。
そこで今回は、知っている人も知らない人も、改めて固定資産の会計処理について全般的におさらいできるようなブログを書きたいと思います。
固定資産の会計処理を全般的におさらい
固定資産に関する会計処理を分類すると次のようになります。
■取得時の会計処理
■保有時の会計処理
■処分時の会計処理
■評価に関する会計処理
これらの項目ごとに会計処理の特徴がありますので、それぞれについて見ていきたいと思います。
取得の会計処理
固定資産を購入すると、固定資産に該当する科目で会計処理を行いますが、具体的なポイントとしては取得価額に含めるものと含めなくても良いものがあります。
企業会計では、購入した資産の本体価額だけでなく、買入手数料、運送費、荷役費、据付費、試運転費等の付随費用を加えて取得原価とするとされていますが、正当な理由がある場合には含めないこともできるとされています。
また税法上も、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などを取得価額に含めるとされています。
税法上も一定の場合には取得価額に含めなくても良い付随費用があります。
理解しやすいように車を買った場合の例を挙げてみます(多くの中小企業が税務上の会計をベースにしているので、税法上の取り扱いを主体に説明します)。
車を購入すると、注文書等に細かく項目が分けられていますので、それぞれの項目ごとに取得価額とするもの、支出時に費用とするものを分けていくことになります。
■取得価額となるもの
・本体
・オプション装備
・自動車税(中古車購入の場合)
・自賠責保険(中古車購入の場合)
※税法上は前オーナーが払った自動車税と自賠責保険の未到来分については、取得価額を構成するとされています
■取得時費用とするもの(していいもの)
・自動車重量税
・法定費用(検査登録、車庫証明
・印紙代
・手続代行費用(検査登録、車庫証明、納車費用)
■その他
・リサイクル関連費用
→リサイクル預託金として別途固定資産に計上
減価償却
固定資産を取得した後は、非償却資産を除き、毎期減価償却費を計上します。
減価償却費については別のブログで解説していますので、詳しくはそちらを参照していただければと思います。
売却の処理
固定資産を売却する際の会計処理を解説します。
固定資産を売却する際は、売却価額と売却時の帳簿価額の差額を売却損益として認識します。
車両の購入時に所有者を下取りに出した際も、固定資産の売却時の会計処理を行い、新しい資産は取得に関する会計処理を行うことになります。
したがって、下取りして新しい資産を購入する際は、取得と売却に切り分けてそれぞれ会計処理を行います。
売却の会計処理で実務上注意が必要なことは、消費税に関する処理です。
固定資産のうち、車両や設備等の売却は課税取引とされますので、売却価額に対して消費税が付加されることになります。
したがって売却損益を計上する際の会計処理を少し工夫しないと、正しく課税売上高を認識できなくなってしまいますので注意が必要です。
仮勘定等を利用し、受取額に対していったん課税売上高を認識した上で税抜金額で売却損益を認識するという、二段階の処理が必要なってきます。
なお、固定資産売却損益は特別損益の区分で処理することが一般的ですが、厳密には特別損益の区分には「臨時かつ巨額」である場合に計上し、それ以外の場合は営業外損益の区分に処理することが理論的には正しい処理と言えます。
除却の処理
たとえばPCを廃棄するなどの固定資産を廃棄処分とした場合等には、除却の会計処理を行います。
具体的には、廃棄時に残っている帳簿価額の金額が除却損として計上されることになります。
こちらの計上区分についても、売却損益と同じ理屈で考えると良いです。
減損会計
減損会計については、個別にブログを書いていますので、そちらをご参考にしていただければと思います。
簡単に解説すると、取得した固定資産の収益性が低下した場合に、その回収可能価額まで減額する処理が減損会計となります。
資産をグルーピングしたり減損の判定をしたりと実務上判断に迷う部分が多い会計処理となります。
あとがき
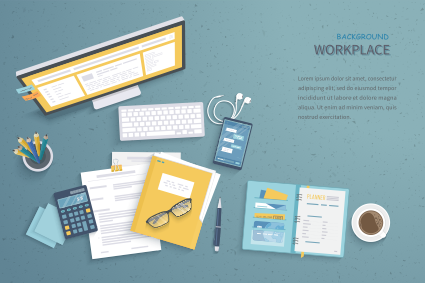
以上が、固定資産に関する会計処理の全般的なおさらいでした。
特に固定資産の取得や売却・処分については、頻繁に発生するものでもないので、その都度処理方法を思い出しながら会計処理を行う人が多いと思いますし、減損会計については会計の深い知識が求められます。
また、これらの部分はなかなか自動化できない会計処理となりますので、個々の事例に合わせて実務担当者がよく検討した上で会計処理を行うことが求められる性質のものと言えますので、それなりの知識と実務経験が必要な分野ではないかなと思います。




